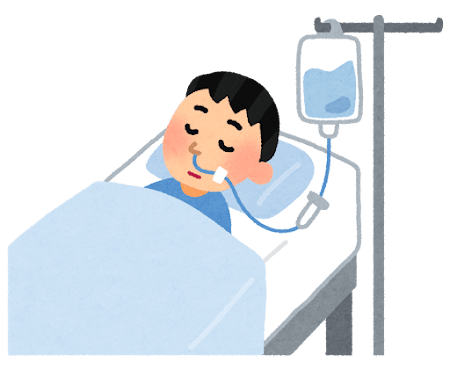当ブログでは、キーパーソンが悩む気持ちを基にタグ付けしています。ぜひほかの記事も読んでみてください。
きちんと向き合いたい このままでいいのか迷っている もっとラクに考えたい 一人で抱えるのは限界 何かを変えたいと思っている 家族の中で孤立している 後悔したくない 情報が足りなくて不安 本人の気持ちを優先したい 決めなきゃいけないけど決められない 疲れていることに気づかれたくない 相手を大切にしたいけど自分も大事にしたい 自分の気持ちに向き合いたい 話しづらい空気を感じている 認知症対応に限界を感じている 誰かに背中を押してほしい 誰にも相談できないまま抱えている
「毎日使っているし、問題なく動いているから大丈夫」
そう思っていたご家族が、ある日突然「酸素が出ていない」と慌てて連絡してきました。確認すると、フィルターが詰まり、流量設定もズレていたのです。看護師として、こうした“なんとなく”の管理が思わぬ事故につながる場面をたびたび見てきました。
在宅酸素療法(HOT)は、ただ機械を使えばいいわけではありません。管理には「理解」と「確認」の積み重ねが不可欠です。本記事では、現場で見かける5つの盲点と、その対策をお伝えします。
HOT管理が不十分になる理由
退院時の説明が曖昧
退院時に一通り説明は受けているものの、「あの時は聞き流してしまった」「用語が難しくて覚えていない」という声が多くあります。実際、退院直後は他の手続きや介護準備で頭がいっぱい。酸素の使用方法は“とりあえず始めてみる”ことが多いのが現状です。
フィードバックのないまま習慣化
自己流のまま操作を続けてしまい、誤った使い方が固定化されてしまうことがあります。「今のところ問題ないから」と確認を後回しにしてしまう傾向も見られます。
機器ごとの違いが曖昧
「酸素って全部同じでしょ?」という認識のまま使用している方もいます。しかし、酸素濃縮器・液化酸素・酸素ボンベにはそれぞれ仕組みや管理方法が異なります。
流量=酸素の量ではない
たとえば流量を自己判断で増やしてしまうと、体に過剰な酸素が入ってしまい、逆に呼吸を抑制することもあります。数値の意味と役割をきちんと把握することが大切です。
「大丈夫だろう」で見逃す異変
日々の中で何も問題が起きていないと、チェックを怠りがちです。機器の異音や焦げ臭さ、流量の変化など、小さなサインを「そのうち直る」と見過ごしてしまうことがあります。
故障の兆しを見逃さない
実際には、このようなサインは重大な故障の前触れであることが多いです。違和感を感じたときは「今動いているからOK」ではなく、「異常かもしれない」と考える意識が必要です。
現場で見かけた5つの盲点
医師の指示なく流量を変える
「少し多めの方がよさそう」「苦しそうだったから」と、自己判断で流量を増やしてしまう例が後を絶ちません。
酸素は薬と同じ、勝手に変えてはいけない
酸素の流量は処方と同じく、医師の管理下で決まっています。安易な調整は症状の悪化を招く恐れがあります。「たった1Lだから」でも、体にとっては大きな違いです。
残量チェックを怠る
液化酸素やボンベは、見た目では残量が分かりにくいことがあります。「まだ使えると思っていたのに切れていた」という声も珍しくありません。
毎日の確認と記録を習慣に
使用開始時にメモを取り、残量の目視確認を習慣づけましょう。目安を決めて早めに交換・充填することが、安全使用の第一歩です。
フィルター清掃の放置
酸素濃縮器はフィルターを通して空気を濃縮しますが、そのフィルターが汚れていると酸素の供給量が減り、火災リスクも高まります。
週1回の簡単な手入れで予防できる
外部フィルターは水洗い、内部フィルターは業者点検に合わせて交換するなど、取扱説明書に基づいた対応を忘れずに。定期的な清掃がトラブルの予防につながります。
異音や異臭を放置する
「音がするけど動いてるから平気」「焦げたようなにおいがするけどまだ使える」——そんなふうに判断していませんか?
早めの通報が命を守る
異音・異臭・過熱などは故障の前兆。小さな異常も無視せず、すぐに業者や医療機関へ連絡を。代替機の準備や、機器の状態確認も同時に行いましょう。
停電時の備えがない
酸素濃縮器は電気が止まると使用できません。停電や災害時に備えていないと、生命に関わる事態になります。
バックアップ機器と避難計画を事前に
非常用ボンベの準備、バッテリー式機器の導入、車載電源の利用など、自宅の環境に合わせた対策を講じましょう。家族間で使用手順を共有しておくことも大切です。
HOT管理をもっとシンプルに、安全に
簡単なルール化がカギ
毎日・毎週の確認項目を「ToDoリスト」にして壁に貼るだけでも、見落としが減ります。家族で分担すれば負担も軽くなり、継続しやすくなります。
「聞く勇気」が事故を防ぐ
「聞くほどのことではない」と思っていたことが、実は大きな盲点だったということも。遠慮せず、訪問看護師や業者に質問してください。
まとめ:不安なままの使用を卒業しよう
HOTは、正しく使えば生活を支える大切な医療です。 でも、「自己流でなんとなく続けている状態」は、安心とは言えません。
チェックリスト:あなたはいくつ当てはまりますか?
- 医師の指示通りに使用している
- 流量・吸入時間の記録がある
- 毎週の清掃・点検を実施している
- 非常時の準備が整っている
- 家族と管理方法を共有している
- 分からないことは都度確認している
1つでも曖昧なら、今が見直しのタイミングです。
あなたのお手入れルーチンはなんですか?ぜひシェアしてくださいね。