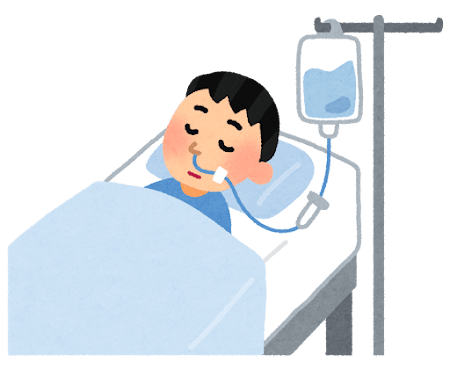当ブログでは、キーパーソンが悩む気持ちを基にタグ付けしています。ぜひほかの記事も読んでみてください。
きちんと向き合いたい このままでいいのか迷っている もっとラクに考えたい 一人で抱えるのは限界 何かを変えたいと思っている 家族の中で孤立している 後悔したくない 情報が足りなくて不安 本人の気持ちを優先したい 決めなきゃいけないけど決められない 疲れていることに気づかれたくない 相手を大切にしたいけど自分も大事にしたい 自分の気持ちに向き合いたい 話しづらい空気を感じている 認知症対応に限界を感じている 誰かに背中を押してほしい 誰にも相談できないまま抱えている
高齢者の「喉詰まり」、その瞬間どう動く?
「ごはん中、父が急に咳き込み出して、声が出なくなって…」
病棟で何度も聞いたことのある場面です。
とくに高齢者は、ちょっとした食べ方や姿勢の変化で喉を詰まらせやすくなります。そして一瞬の判断が、その後の命に関わることも。
この記事では、窒息のサインを早く見つけるための視点や、すぐに試せる応急処置の方法、救急車を呼ぶか迷ったときの判断ポイントを紹介します。
ふだんは穏やかな夕食の時間。
そんなときに「まさか」が起こることもあります。
でも、あわてず動くための準備は、今からでもできます。
見逃さない!窒息のサインとは
声が出ない、苦しそう、それは窒息かも
食事中に急な沈黙や強い咳き込みが見られたら、まず窒息を疑ってください。
- 咳が続く
- 声が出ない、話せない
- 顔が青白くなる、唇が紫になる
- 手で喉を押さえるような仕草
病棟でも、これらのサインは見逃せないポイントとして共有されます。
高齢者に多い窒息の原因
実際に窒息を引き起こす食べ物には、共通点があります。
- もち、白玉、団子などの粘着性食品
- パサついたパンや焼き魚の骨
- ピーナッツなどの小粒のもの
また、入れ歯の不具合や嚥下反射の衰えがある方は、詰まりやすくなります。
応急処置の基本は「すぐ動く」
背中を叩く?お腹を押す?判断のコツ
まずは、意識があるかどうかを確認してください。
意識がある場合:
- 背部叩打法:背中の肩甲骨の間を5回強く叩く
- ハイムリック法:おへその上を拳で押し上げるように圧迫
意識がない場合:
- **心肺蘇生法(CPR)**を実施
- すぐに救急車を要請
※高齢者には骨折リスクもあるため、力加減や体勢にも注意が必要です。
実際の現場ではこう判断します
ある日のこと。
嚥下機能が低下していた女性が、餅を喉に詰まらせました。
職員はすぐに背中を叩き、出なかったためハイムリック法へ。
その場で解消できたものの、判断と対応が1分遅れていたら命に関わっていたかもしれません。
救急車を呼ぶべき3つの状況
このサインが見えたら、すぐ119
- 反応がない
- 呼吸していない
- 応急処置をしても改善しない
呼吸停止は1分ごとに脳ダメージが進行します。
「念のため」でも、迷ったら呼ぶほうが安全です。
救急隊に伝えるべきこと
通報時に伝えるとよい情報:
- 状況(何を食べていて、どうなったか)
- 応急処置の内容(背中を叩いた、ハイムリック法を行った 等)
- 既往歴や服薬内容、アレルギーの有無
落ち着いて答えるのは難しい場面ですが、事前にメモやカードを準備しておくと安心です。
まとめ:窒息対応、今から備える6つの視点
- 食事中の様子に「いつもと違う」があれば即対応
- 詰まりやすい食品を家庭内で把握しておく
- 応急処置の方法を家族全員で確認する
- 意識や呼吸の有無で救急車の判断をする
- 救急通報時のポイントを事前に共有しておく
- 普段から「食べる環境」も整えておく(姿勢、スピード等)
今すぐできる準備として、**「応急処置を貼った冷蔵庫メモ」や「緊急連絡カード」**の作成もおすすめです。
ご感想や体験談があれば、ぜひコメント欄で教えてください。
「この情報が役に立ちそう」と思ったら、SNSでのシェアも大歓迎です。
このページをブックマークしておけば、いつでも確認できます。
いざという時の安心のために、ぜひ保存しておいてください。
不安になったら、一人で抱え込まず、この記事を開いて確認しましょう。
他にも、下記テーマの記事があります。
- こけるときはこける、ケガをさせないことが大事
- その治療、本当に必要ですか?
- その薬、本当に必要ですか?
- もう解放されたいと思うその気持ち、持っていていいんです!
- カロリー重視でOK
- キーパーソンとは
- ケアマネージャーとは
- 人工肛門について
- 介護のSOS
- 介護保険のはなし
- 入所型施設について
- 包括支援センターと保健師
- 医療保険について
- 吸引について
- 圧迫骨折は入院させないのもひとつの手
- 在宅酸素について
- 排泄だけがネックなら、受け入れる覚悟を持とう
- 病院について
- 看護小規模多機能
- 経管栄養について
- 認知症に悩むあなたへ:在宅編
- 認知症に悩むあなたへ:病院、施設編
- 通所型施設について
- 高齢者はより感覚的で、感情で生きている
あなたのケアの一歩が、明日の安心につながりますように。