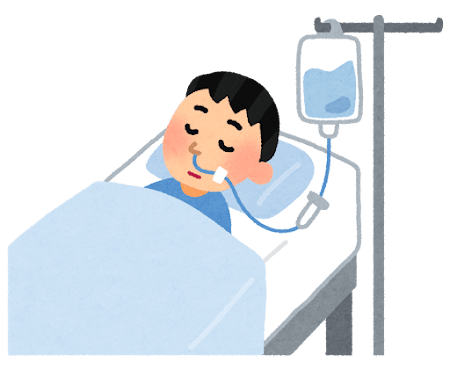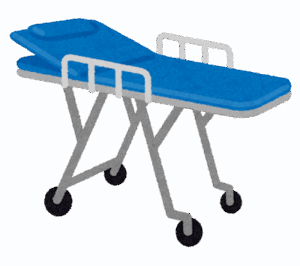当ブログでは、キーパーソンが悩む気持ちを基にタグ付けしています。ぜひほかの記事も読んでみてください。
きちんと向き合いたい このままでいいのか迷っている もっとラクに考えたい 一人で抱えるのは限界 何かを変えたいと思っている 家族の中で孤立している 後悔したくない 情報が足りなくて不安 本人の気持ちを優先したい 決めなきゃいけないけど決められない 疲れていることに気づかれたくない 相手を大切にしたいけど自分も大事にしたい 自分の気持ちに向き合いたい 話しづらい空気を感じている 認知症対応に限界を感じている 誰かに背中を押してほしい 誰にも相談できないまま抱えている
転倒もしていない、痛みもなさそう。それでも、ベッドのそばで力なくうずくまっていたあの方を見つけたとき、私は「何かがおかしい」と感じました。「今日は、体が動かないの」と小さくつぶやかれたのを、今も忘れられません。
こうした状況は、在宅介護の現場では決して珍しくありません。特におひとりで介護を担っている方にとっては、「これって救急車を呼ぶべき?」「様子を見ても大丈夫?」と、判断に迷うことも多いはずです。
この記事では、「動けない=すぐに119番」ではないけれど、見逃してはいけないサインを5つ、現場経験をもとにお伝えします。焦らず、でも油断せず。大切な人を守るために、必要な視点と行動を一緒に整理していきましょう。
動けない理由を知ることが、最初の一歩です
高齢者が突然動けなくなると、多くの人は「ケガ?」と考えます。でも、原因は見た目では分からないこともあるのです。
一見軽く見えてしまう身体的な原因
「筋肉痛?」「寝違えただけ?」そんなふうに思ってしまいがちですが、実は深刻なサインであることも。
転倒やケガによるもの
「転んでない」と言われても、無意識に隠してしまう方も多いです。腕の位置、足のつき方、表情の違和感を見逃さないでください。
関節や筋肉の不調
関節リウマチの再燃、筋力低下、強いこわばりなどが原因になることも。いつも通り動けないこと自体が、SOSのサインです。
見えにくい「脳の異常」
深刻な症状なのに、外からは分かりにくいのが脳の異常です。
脳梗塞や一過性脳虚血発作(TIA)
「顔がゆがんでいる」「言葉が出ない」「視線が合わない」など、ささいな変化が見逃せないポイントです。
けいれん後の意識もうろう
発作のあとのぼんやり状態は、単なる「疲れ」や「眠気」と間違えられがち。でも、数時間続くようなら注意が必要です。
体内からくる異変
外見では分からないけれど、体の中で大きな変化が起きていることもあります。
血糖値の異常
糖尿病がある方は、低血糖・高血糖どちらでも「動けない」症状が出ることがあります。計測できるなら、すぐ確認してみましょう。
脱水・感染症
「脱水なんて…」と思われるかもしれませんが、高齢者にとっては軽い脱水や尿路感染が「意識障害」や「歩行不能」につながることもあります。
救急車を呼ぶべき「5つの赤信号」
ここからは、私が実際に「すぐに119番すべき」と判断する5つのサインをお伝えします。
意識がいつもと違う
「寝ぼけてるだけ?」「昨日もこんな感じだったかも?」——そう思ってしまう前に、チェックしてほしいポイントがあります。
呼びかけに反応が薄い
名前を呼んでもすぐに反応しない、視線が合わないといった様子があれば、すぐに様子を見るのをやめましょう。
混乱している
「今どこにいるの?」「今日は何日?」といった質問に答えられない場合は、脳の異常の可能性を疑います。
激しい痛みを訴えている
言葉では我慢していても、体は痛みを正直に示しています。
胸・お腹・背中の痛み
心臓・胃腸・大動脈など命に関わる臓器の問題が潜んでいる可能性があります。
痛みで体が動かない
触れるだけで身を引くような反応や、「深呼吸もできない」ような状態は、救急の対象です。
ケガ・出血がある
外傷が目立たなくても、実は深刻な状態が隠れていることも。
骨折が疑われる
腕や足が変な角度になっていたり、立たせようとすると強い痛みを訴える場合は、無理に動かさず通報を。
出血が止まらない
皮膚の浅い傷でも、血が止まりにくくなる薬を飲んでいる方は注意が必要です。
呼吸が苦しそう
「息苦しい」は見た目で分かりにくいことも。以下の様子が見られたら要注意です。
息が浅く速い
肩で呼吸していたり、話すのがしんどそうだったりする場合は、すぐに判断を。
息をしているのか分からない
胸の動きが小さい、リズムが乱れている場合は、迷わず119番です。
「何かおかしい」と感じる
理由はうまく説明できないけれど、「これは今までと違う」と思ったとき——その直感は、大切にしてください。
見た目や様子が急に変わった
朝までは普通に話していたのに、突然ぼんやりしてきた、立てなくなった——こうした変化があるときは、すぐ相談を。
「なんとなく変」と感じた
介護者であるあなたは、誰よりも日々の様子を知っています。その違和感を無視せず、声に出してみてください。
救急車を待つ間にできること
通報後の数分間も、あなたの行動が大切な支えになります。
安全確保と、無理な移動をしないこと
転倒やケガを防ぐため、環境を整えることから始めましょう。
周囲の物をどかす
鋭利な物、壊れ物、足元にあるコード類などを片づけてください。
身体の安定をサポート
枕や毛布で頭を支えたり、姿勢を整えて呼吸がしやすい状態に。
呼吸や意識を観察する
特別な機器がなくても、「見て、聞いて、声をかける」だけで十分です。
呼吸の様子を確認
速さ、深さ、リズムの乱れがないか注意して見守ります。
声かけの反応を見る
名前を呼んだときに目が合うか、手を握り返してくるか、などで意識レベルを把握しましょう。
落ち着ける声かけと保温
医療者が到着するまでの間、不安を和らげることも大切なケアです。
毛布やタオルで体温を守る
特に冬場や体が冷えているときは、やさしく保温を。
安心できる声かけ
「もうすぐ救急車が来ますよ」「一緒にいますよ」と声をかけ続けてください。
救急隊員に伝えるべきこと
情報が正確に伝わるほど、対応がスムーズになります。
いつ、何が起きたか
時間を具体的に伝える
「10分前」「昼食後すぐ」など、はっきりしたタイミングが鍵です。
起こった順番を説明する
「突然立てなくなった」「ふらついて座り込んだ」など、流れを簡潔に話せると理想的です。
基礎疾患と服薬の情報
持病を整理して伝える
脳梗塞や心臓病、糖尿病などは特に重要です。
現在の薬とアレルギー
「飲み薬のリスト」や「薬の説明書」を一緒に渡すとスムーズです。
その場で答えられる準備を
質問に落ち着いて対応
救急隊員からの問いに冷静に答えられるよう、深呼吸して待ちましょう。
保険証や書類の準備
緊急連絡先や病院の診察券も、あらかじめ1か所にまとめておくと安心です。
まとめ:あなたの判断は間違っていません
「大げさだったかも…」と不安に思う必要はありません。
迷って調べたその時点で、あなたは大切な人を守るために動いているのです。
✔︎ 意識がぼんやりしていませんか?
✔︎ 呼吸に異常はありませんか?
✔︎ 激しい痛みを訴えていませんか?
✔︎ 外傷や出血は見られませんか?
✔︎ いつもと様子が違うと感じませんか?
ひとつでも当てはまるなら、ためらわず119番。
それは「間違い」ではなく、後悔を防ぐ行動です。
「#7119」もあります。急な病気や怪我で救急車を呼ぶべきか、病院を受診すべきか、判断に迷ったときに利用できる電話相談窓口です。看護師などが電話で相談を受け、緊急度や対処法についてアドバイスをしてくれます。
地域によっては利用できない場合もあるため、お住まいの自治体で対応状況をご確認ください。
💬 この内容が役に立ったと感じたら、ぜひシェアやコメントをお寄せください。
あなたの声が、どこかで誰かを助けるかもしれません。
このページをブックマークしておけば、いつでも確認できます。
いざという時の安心のために、ぜひ保存しておいてください。
不安になったら、一人で抱え込まず、この記事を開いて確認しましょう。
他にも、下記テーマの記事があります。
- こけるときはこける、ケガをさせないことが大事
- その治療、本当に必要ですか?
- その薬、本当に必要ですか?
- もう解放されたいと思うその気持ち、持っていていいんです!
- カロリー重視でOK
- キーパーソンとは
- ケアマネージャーとは
- 人工肛門について
- 介護のSOS
- 介護保険のはなし
- 入所型施設について
- 包括支援センターと保健師
- 医療保険について
- 吸引について
- 圧迫骨折は入院させないのもひとつの手
- 在宅酸素について
- 排泄だけがネックなら、受け入れる覚悟を持とう
- 病院について
- 看護小規模多機能
- 経管栄養について
- 認知症に悩むあなたへ:在宅編
- 認知症に悩むあなたへ:病院、施設編
- 通所型施設について
- 高齢者はより感覚的で、感情で生きている
あなたのケアの一歩が、明日の安心につながりますように。