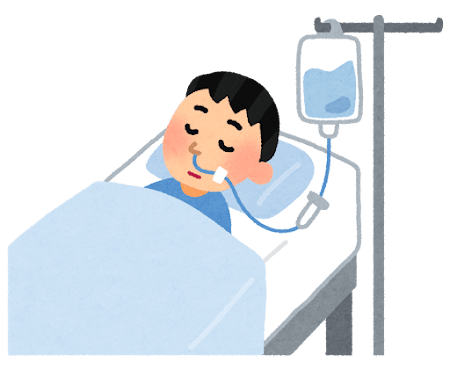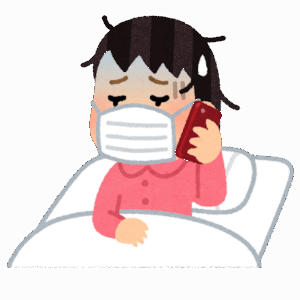当ブログでは、キーパーソンが悩む気持ちを基にタグ付けしています。ぜひほかの記事も読んでみてください。
きちんと向き合いたい このままでいいのか迷っている もっとラクに考えたい 一人で抱えるのは限界 何かを変えたいと思っている 家族の中で孤立している 後悔したくない 情報が足りなくて不安 本人の気持ちを優先したい 決めなきゃいけないけど決められない 疲れていることに気づかれたくない 相手を大切にしたいけど自分も大事にしたい 自分の気持ちに向き合いたい 話しづらい空気を感じている 認知症対応に限界を感じている 誰かに背中を押してほしい 誰にも相談できないまま抱えている
深夜2時過ぎ、病棟の電話が鳴りました。
「母の呼吸が変なんです…。救急車、呼んだほうがいいですか?」
ひとりでお母さんを介護する女性の声は、不安に揺れていました。私はリハビリ病棟で働く看護師として、こうした“夜中の迷い”に何度も向き合ってきました。
この記事では、そんな不安に寄り添いながら、「本当に呼ぶべきか迷ったとき」に役立つ7つの備えを紹介します。
- 急変に気づいたら、どう判断する?
- 救急車を呼ぶべき症状って?
- 事前に準備しておくべきこととは?
「もしものときに、ちゃんと対応できるかな」
そんな思いを抱えるあなたのために、現場の視点で実践的にお届けします。
なぜ緊急対応の備えが重要なのか
夜間は、体調が悪化しやすいだけでなく、相談先が限られている時間帯です。
「朝まで様子を見ても大丈夫だろう」と思ってしまいがちですが、それが命取りになることもあります。
介護者の多くが、「これは大丈夫」「ちょっとした疲れかも」と迷ってしまうのが現実です。
でも、備えがあれば、“行動に移せる自分”をつくることができます。
医療の知識よりも大切なのは、「何を見るべきか」「どう行動するか」の具体的なステップです。
夜間の高齢者介護で起こりやすい“見落とし”
特に夜は、疲労や暗さもあり、小さな変化に気づきにくくなります。
「ちょっと呼吸が浅い?」「声をかけても反応が鈍い気がする…」そんな不安を抱えても、つい様子を見てしまう方も多いのではないでしょうか。
しかし、その“少しの変化”が、実は重大なサインだったということも少なくありません。
判断に迷ったときに行動を後押ししてくれるのが、「自分でつくるチェックリスト」です。
緊急対応キットを整えよう
私たち医療者が病院で最初に確認するのは、「何が起きたか」だけではありません。
**患者さんの持病や服薬状況、過去の経過など“背景情報”**があることで、より早く正確な対応ができます。
このような場面を想定し、以下の3つを備えておくと安心です:
- 連絡先リスト
- 医療・服薬情報
- 緊急時の行動フロー(手順書)
連絡先リストは紙とスマホの両方に
最低限、以下の情報は一覧にして、すぐ見える場所に貼っておきましょう。
- 主治医の名前と診療時間
- 最寄りの救急病院
- ケアマネジャーや訪問看護の連絡先
- 救急相談窓口(例:#7119)
- かかりつけ薬局の番号
玄関や冷蔵庫、電話機のそばなど、目につきやすい場所がおすすめです。
医療情報は1枚にまとめておこう
いざという時に「薬の名前が分からない」「どんな病気があったっけ?」と慌ててしまうことがあります。
そのようなときのために、次の情報をA4用紙1枚にまとめておきましょう。
- 現在の病名・診断名
- 服用中の薬(薬名・用量)
- アレルギーの有無
- 延命に関する希望(ある場合)
家族が話せなくても、この紙が“本人の代弁者”になります。
緊急時の行動チェックリスト
パニック時は、頭が真っ白になってしまうこともあります。
そんな時こそ、「何をするか」が書かれたチェックリストが力を発揮します。
- 救急車を呼ぶ症状の目安
- 通報時に伝えるべき情報(症状・年齢・状況)
- 呼び出し後にやるべき準備(玄関の施錠解除・ペットの対応など)
スマホのメモでもOKですが、紙にして壁に貼っておくと誰でも使えます。
救急車を呼ぶべき“5つの症状”
「救急車を呼ぶべきかどうか」は、最も迷いやすいポイントです。
以下の症状が見られたら、迷わず通報するのがおすすめです。
- 呼びかけに反応しない
- 呼吸が浅い・不規則・止まりそう
- 胸の痛み、脈の乱れ
- 顔がゆがむ、ろれつが回らない、片手が上がらない
- 明らかに様子がおかしい(急な混乱、異常な汗など)
こうした症状は、脳卒中や心筋梗塞のサインかもしれません。
落ち着きを取り戻す“3ステップ”
判断に迷ったら、次のように行動してみてください。
- 深呼吸を1回
- チェックリストを手に取る
- 書かれている通りに読んで対応
準備しておいた手順が、動揺する気持ちを支えてくれます。
看護師が“まず見るポイント”とは
私たちが患者さんを見たときに最初に確認するのは、「いつもと違う」という変化です。
- 顔色は?(白っぽくないか、青ざめていないか)
- 呼吸は?(浅い・速い・止まりがちではないか)
- 意識は?(名前を呼んで反応があるか)
これらは医療知識がなくても、日常を知るあなたが一番気づけることです。
後悔を減らすために「今」できること
「もっと早く気づいていれば…」
「様子を見るべきじゃなかった」
そう後悔する方を、私は何人も見てきました。
ですが、この記事を読んでくださっているあなたには、そうなってほしくありません。
実際のケースが教えてくれたこと
あるご家族は、「ただ疲れているのかも」と判断して数時間様子を見てしまいました。
結果、救急搬送時には症状が進行しており、回復までに長い時間がかかりました。
今では、その方は冷蔵庫に緊急連絡先と手順シートを貼って、いざという時に備えています。
「知っていればできたのに」を減らすために
この記事は、介護者の「知らなかった」を埋めるために書きました。
情報は行動に変わり、行動は安心を生みます。
あなたも、今日からできることを1つだけでも始めてみませんか?
まとめ:今すぐできる“7つの備え”
- ✅ 主治医・救急・相談先の連絡先を一覧に
- ✅ 服薬・病歴・アレルギー情報を1枚にまとめる
- ✅ 緊急時の手順チェックリストを用意
- ✅ 危険なサインを把握しておく
- ✅ 紙ベースの情報を玄関など見える場所に置く
- ✅ 家族・ヘルパーにも共有しておく
- ✅ 夜間の急変に備えてシミュレーションしておく
あなたの小さな一歩が、大きな安心につながります。
よければ、#介護SOSの備え のタグでシェアやコメントをお寄せください。
あなたの備えが、誰かの支えになりますように。
このページをブックマークしておけば、いつでも確認できます。
いざという時の安心のために、ぜひ保存しておいてください。
不安になったら、一人で抱え込まず、この記事を開いて確認しましょう。
他にも、下記テーマの記事があります。
- こけるときはこける、ケガをさせないことが大事
- その治療、本当に必要ですか?
- その薬、本当に必要ですか?
- もう解放されたいと思うその気持ち、持っていていいんです!
- カロリー重視でOK
- キーパーソンとは
- ケアマネージャーとは
- 人工肛門について
- 介護のSOS
- 介護保険のはなし
- 入所型施設について
- 包括支援センターと保健師
- 医療保険について
- 吸引について
- 圧迫骨折は入院させないのもひとつの手
- 在宅酸素について
- 排泄だけがネックなら、受け入れる覚悟を持とう
- 病院について
- 看護小規模多機能
- 経管栄養について
- 認知症に悩むあなたへ:在宅編
- 認知症に悩むあなたへ:病院、施設編
- 通所型施設について
- 高齢者はより感覚的で、感情で生きている
あなたのケアの一歩が、明日の安心につながりますように。