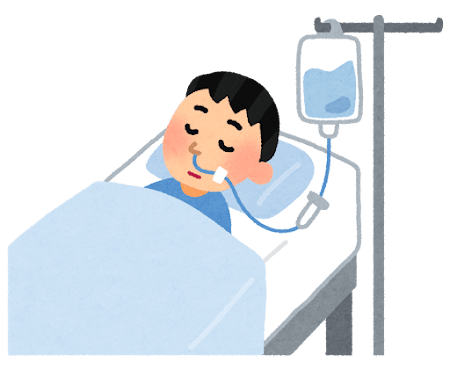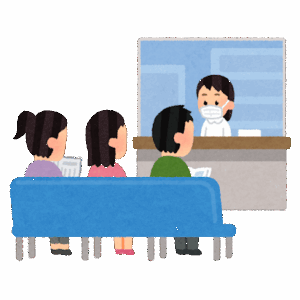当ブログでは、キーパーソンが悩む気持ちを基にタグ付けしています。ぜひほかの記事も読んでみてください。
きちんと向き合いたい このままでいいのか迷っている もっとラクに考えたい 一人で抱えるのは限界 何かを変えたいと思っている 家族の中で孤立している 後悔したくない 情報が足りなくて不安 本人の気持ちを優先したい 決めなきゃいけないけど決められない 疲れていることに気づかれたくない 相手を大切にしたいけど自分も大事にしたい 自分の気持ちに向き合いたい 話しづらい空気を感じている 認知症対応に限界を感じている 誰かに背中を押してほしい 誰にも相談できないまま抱えている
「今週も3回病院」「本人も私もヘトヘト」——これは、ある娘さんの一言です。
高齢の母のために毎週病院へ。気づけば、生活の軸が“医療中心”になっていたそうです。
この記事では、医療依存に気づいた家族がどのように“通院ありき”の生活から抜け出したのかを紹介します。
医療を否定するのではなく、“必要な医療”とのちょうどいい距離を探るための実践的ヒントをお届けします。
医療依存に気づくきっかけ
「念のため通院」の積み重ねが生活を圧迫
体調の不安、医療者のすすめ、家族の責任感。そのすべてが“通院”という行動を正当化しがちです。
でも、その回数や内容、きちんと整理できていますか?
不安を安心に変えるには“目的の明確化”が第一歩
「何のための通院か?」と自問してみてください。
なんとなく通っている場合、医師に「今後どう進めるか」を相談するだけでも見える景色が変わります。
介護者自身の“義務感”が選択肢を狭めることも
「行かないと悪くなる気がする」「家族だから頑張らないと」。
そう思い込むことで、かえって疲弊していませんか? 本人も介護者も、心と体に余裕がなければ良い判断はできません。
“通院を減らす”ことは手抜きではなく、選択肢の一つ
医療だけでなく、生活支援や地域資源も選べる時代です。
“自分たちにちょうどいい支え”を見つける視点が大切です。
「医療以外」に目を向ける視点
医療の代替ではなく、補完という考え方
訪問診療や看護、薬剤師の服薬サポートなど、在宅でも安心できる医療体制はあります。
「行かなければ診てもらえない」は、もう過去の話です。
主治医とケアマネを巻き込んでプランを立てる
「通院を減らしたい」「在宅でも診てほしい」——その希望は、思っているよりも多くの医療者が受け止めてくれます。
まずは、遠慮せずに相談することから始めましょう。
本人の“声なき希望”を聞く
「もう通いたくない」とは、なかなか本人の口からは出てきません。
だからこそ、日々の様子や反応に目を向ける観察力が求められます。
「今日も病院?」という表情を見逃さない
食欲、睡眠、表情…。少しでも“負担そう”なら、立ち止まって選択肢を一緒に考える機会です。
実際に選ばれた5つの工夫
通院の意味を整理する
毎回の目的を主治医と再確認。「必要」と「習慣」の区別ができるだけで、見える世界が変わります。
訪問診療に切り替える
週3回の通院がゼロになったケースも。移動がなくなり、本人の生活リズムが整いました。
家族の予定も優先に
「介護は生活の一部」と考え直し、家族の時間も大切にする選択へ。無理をしない覚悟が笑顔を増やしました。
医師との関係性を育てる
「頻度はどう見直せますか?」といった問いかけをためらわずに。関係が築けると、よりよい判断が可能に。
ケアマネを中心に連携する
医療と生活の橋渡し役としてケアマネが機能することで、通院の負担が分散され、支援の幅が広がります。
まとめ:医療と暮らし、どちらも大切に
医療を否定せず、でも依存しすぎずに向き合う——それが、これからの介護に求められる視点です。
無理をしないこと。問い直すこと。周囲に頼ること。これらはすべて“安心して暮らす”ための選択肢です。
チェックリスト:通院の負担に気づく5つのサイン
- □ 何のための通院かわからない
- □ 本人が通院をしんどがっている
- □ 家族が生活リズムを崩している
- □ 通院の合間に他の予定を入れられない
- □ 医療者以外に相談していない
どれか一つでも当てはまったら、今こそ“暮らしの中の医療”を見直すチャンスです。
この記事が気づきのきっかけになったら、ぜひSNSでシェアしてくださいね。コメントも大歓迎です。
このページをブックマークしておけば、いつでも確認できます。
いざという時の安心のために、ぜひ保存しておいてください。
不安になったら、一人で抱え込まず、この記事を開いて確認しましょう。
他にも、下記テーマの記事があります。
- こけるときはこける、ケガをさせないことが大事
- その治療、本当に必要ですか?
- その薬、本当に必要ですか?
- もう解放されたいと思うその気持ち、持っていていいんです!
- カロリー重視でOK
- キーパーソンとは
- ケアマネージャーとは
- 人工肛門について
- 介護のSOS
- 介護保険のはなし
- 入所型施設について
- 包括支援センターと保健師
- 医療保険について
- 吸引について
- 圧迫骨折は入院させないのもひとつの手
- 在宅酸素について
- 排泄だけがネックなら、受け入れる覚悟を持とう
- 病院について
- 看護小規模多機能
- 経管栄養について
- 認知症に悩むあなたへ:在宅編
- 認知症に悩むあなたへ:病院、施設編
- 通所型施設について
- 高齢者はより感覚的で、感情で生きている
あなたのケアの一歩が、明日の安心につながりますように。