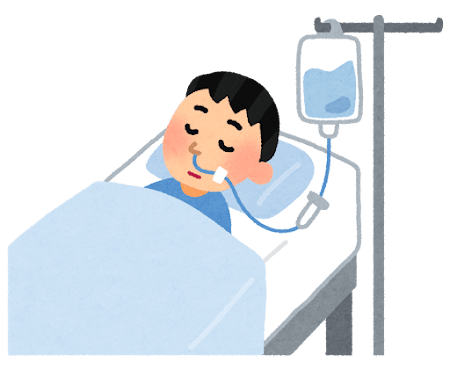当ブログでは、キーパーソンが悩む気持ちを基にタグ付けしています。ぜひほかの記事も読んでみてください。
きちんと向き合いたい このままでいいのか迷っている もっとラクに考えたい 一人で抱えるのは限界 何かを変えたいと思っている 家族の中で孤立している 後悔したくない 情報が足りなくて不安 本人の気持ちを優先したい 決めなきゃいけないけど決められない 疲れていることに気づかれたくない 相手を大切にしたいけど自分も大事にしたい 自分の気持ちに向き合いたい 話しづらい空気を感じている 認知症対応に限界を感じている 誰かに背中を押してほしい 誰にも相談できないまま抱えている
「これ、うちにも必要だったかも…」
そんな後悔を、あなたにはしてほしくありません。
医療的なケアが必要になってきた親を、できるだけ自宅で支えたい。そう願う一方で、「どこまで家で対応できるのか」「制度やサービスの仕組みが分からない」――そんな不安や迷いを抱える方も多いのではないでしょうか。
看護小規模多機能型居宅介護(通称:看多機)は、訪問看護・訪問介護・通い・宿泊などを柔軟に組み合わせて、医療ニーズの高い高齢者が地域で安心して暮らせるよう支援するサービスです。
この記事では、看多機を利用できる「5つの条件」をやさしく整理してお伝えします。介護経験の浅い方でも安心して読める内容です。
看多機を利用できる5つの条件
1. 要介護・要支援の認定があること
介護保険制度において、「要支援1~2」「要介護1~5」の認定を受けていることが前提です。
「まだそんなに重くないから…」と遠慮せず、必要があれば申請してみましょう。
- 定期的にケアマネージャーと状態を確認
- 状態の変化があれば、再認定の申請を検討
2. 医療的なケアが必要な状態であること
看多機は、医療ニーズが高くても在宅生活を続けたい方を支えるサービスです。
- 酸素療法・インスリン・創傷ケア・胃ろう・気管切開・終末期ケアなどにも対応
- 看護師による訪問があるため、専門的な医療処置も在宅で可能
3. サービス対象地域に住んでいること
看多機は、利用できる地域が限られています。施設からおおよそ30分以内が目安です。
- たとえば「〇〇市の△△看多機」など、自治体ごとに対応施設が異なります
- 市町村の高齢福祉課やケアマネに、対象エリアか確認を
4. ケアマネージャーとの連携が取れていること
看多機の利用には、ケアマネの関与が不可欠です。
- ケアプランの調整や申し込みの窓口にも
- 現状や希望をしっかり共有することが、第一歩になります
5. 必要書類や医療情報が準備できていること
スムーズな導入のためには、事前準備がカギを握ります。
- 介護保険証、医師の意見書、薬の情報などを整理
- 書類がそろっていると、緊急時の対応も迅速に
なぜ今「対象条件」を知っておくべきなのか?
チャンスを逃さないために
「もっと早く知っていれば…」という声は、現場では決して少なくありません。
特に病院から自宅への移行時、看多機のようなサービスを検討しておくと選択肢が広がります。
家族の負担を減らすために
一人での介護が限界に感じたとき、看多機の24時間体制は心強い味方に。
「通い」「泊まり」「訪問看護」など、必要な支援を組み合わせて使えるのが特徴です。
いざという時に慌てないために
急な体調悪化や退院のタイミングでも、準備ができていれば焦らず対応できます。
ケアマネとの早めの連携が、将来の安心につながります。
おわりに:今できる一歩とは?
最後に、看多機を利用するための5つの条件をもう一度整理します。
- 要介護・要支援の認定がある
- 医療的なケアが必要
- 対象地域に住んでいる
- ケアマネとの連携が取れている
- 必要書類や情報の準備ができている
「うちの場合はどうだろう?」と少しでも思ったら、まずはケアマネに一言声をかけてみてください。
または、地域包括支援センターに電話するだけでも、第一歩になります。
あなたの行動が、ご家族の未来を変えるかもしれません。
このページをブックマークしておけば、いつでも確認できます。
いざという時の安心のために、ぜひ保存しておいてください。
不安になったら、一人で抱え込まず、この記事を開いて確認しましょう。
他にも、下記テーマの記事があります。
- こけるときはこける、ケガをさせないことが大事
- その治療、本当に必要ですか?
- その薬、本当に必要ですか?
- もう解放されたいと思うその気持ち、持っていていいんです!
- カロリー重視でOK
- キーパーソンとは
- ケアマネージャーとは
- 人工肛門について
- 介護のSOS
- 介護保険のはなし
- 入所型施設について
- 包括支援センターと保健師
- 医療保険について
- 吸引について
- 圧迫骨折は入院させないのもひとつの手
- 在宅酸素について
- 排泄だけがネックなら、受け入れる覚悟を持とう
- 病院について
- 看護小規模多機能
- 経管栄養について
- 認知症に悩むあなたへ:在宅編
- 認知症に悩むあなたへ:病院、施設編
- 通所型施設について
- 高齢者はより感覚的で、感情で生きている
あなたのケアの一歩が、明日の安心につながりますように。