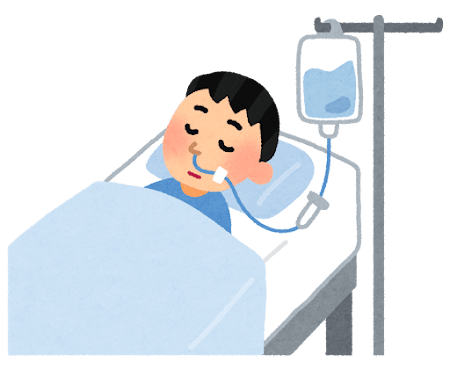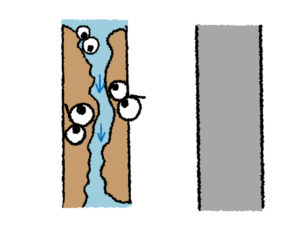当ブログでは、キーパーソンが悩む気持ちを基にタグ付けしています。ぜひほかの記事も読んでみてください。
きちんと向き合いたい このままでいいのか迷っている もっとラクに考えたい 一人で抱えるのは限界 何かを変えたいと思っている 家族の中で孤立している 後悔したくない 情報が足りなくて不安 本人の気持ちを優先したい 決めなきゃいけないけど決められない 疲れていることに気づかれたくない 相手を大切にしたいけど自分も大事にしたい 自分の気持ちに向き合いたい 話しづらい空気を感じている 認知症対応に限界を感じている 誰かに背中を押してほしい 誰にも相談できないまま抱えている
はじめに
「経管栄養が流れない……これってすぐ病院に連絡したほうがいい?」
ある日、在宅介護をされているご家族からこんな連絡がありました。何度か注入を試しても、うまく入らない。シリンジを変えてみても、やっぱり詰まっている感じがする。けれど、急いで動いていいのか迷う——そのお気持ち、よくわかります。
この記事では、経管栄養が詰まったときに迷わず動くための5つの判断の視点を、現場経験のある看護師の視点で解説します。原因、対処法、受診のタイミング、そして日々できる予防策まで網羅しています。
経管栄養が詰まる3つの原因とは?
栄養剤の固まりや凝固
注入後すぐに洗浄せずに時間が経つと、栄養剤がチューブ内で固まってしまうことがあります。特に、たんぱく質や食物繊維が多く含まれた製品は固まりやすい傾向にあります。
「ほんの数分だから大丈夫」と油断しがちですが、体温の影響で固まりやすくなることもあります。栄養注入後は、ぬるま湯(20〜30mL)でのフラッシュを習慣にすることで、詰まりの予防につながります。
チューブの折れやねじれ
急に流れなくなった場合、チューブの折れやねじれが原因のことも少なくありません。寝返りや移乗の際に、知らぬ間に体の下敷きになっていたり、衣服で押されて曲がっていたりするケースはよくあります。
まずは落ち着いて、チューブの外側全体を確認し、物理的な圧迫がないかをチェックしてみましょう。
薬や水の使い方による詰まり
粉薬を溶かすときにしっかり混ぜていなかったり、洗浄用の水が少なかったりすると、細かい粒子がチューブに残って詰まりの原因になります。
「薬は入れたけど水で流さなかった」「今日は時間がなくてフラッシュを飛ばしてしまった」——そんな日が続くと、目に見えない詰まりが蓄積することもあります。
自宅でできる安全な対処法
ぬるま湯でのやさしいフラッシュ
「もう少し押し込めば入るかも」と思う気持ち、よくわかります。しかし、力任せはかえって危険です。
まずはぬるま湯を少量入れ、軽くシリンジを押し引きするようにして、詰まりをふやかす方法を試してみましょう。
それでも抵抗が強いと感じたら、それ以上は無理をせず、次のステップに移る判断を。
体勢を変える・チューブを整える
栄養剤が流れにくいときは、身体の向きやチューブの角度が関係していることもあります。
たとえば、ベッドの背を少し上げる、体を左右に軽く傾けるなど、小さな体位変換で流れが改善することがあります。
また、チューブの外側を指でなぞって、折れやつぶれがないか確認してみてください。
器具(シリンジや注入器)の交換
詰まっているように見えて、実はシリンジが劣化していただけというケースもあります。
押し棒が固かったり、空気が混じっていたりすることで、スムーズに注入できない場合があります。思いきって器具を新しくすることで改善することも多いので、道具の状態にも目を向けましょう。
迷ったとき、相談すべき3つのサイン
対処しても改善しないとき
ぬるま湯でのフラッシュや体勢調整を何度か試しても、状況が変わらないときは、これ以上無理を続けないことが大切です。
「また今度試そう」と様子見しているうちに、ご本人の体調が崩れてしまうことも。限界を感じたら、そこで止まる勇気も必要です。
嘔吐・腹痛・尿量減少などの変化
詰まりが原因で、お腹が張っている、吐き気がある、水分が入らず尿が出ていないなどの症状があれば、それはただの詰まりではなく、体調不良のサインです。
こうした変化があるときは、すぐにかかりつけ医や訪問看護師に相談を。ためらうより、早めの連絡が安心につながります。
「このままでいいのか」と不安なとき
目に見える異常がなくても、介護している自分の中に「このままでいいのかな」という違和感があるときは、無理に我慢せずに動いてください。
誰かに聞いてもらうことで、「大丈夫な詰まり」なのか、「病院に連絡すべき詰まり」なのかが見えてきます。
内服薬の確認も忘れずに
経管栄養が詰まって注入できないとき、内服薬の投与時間や間隔がずれることによる影響にも注意が必要です。
中には、毎日決まった時間に服用することで、血中濃度を安定させることが前提になっている薬もあります。服薬のタイミングがずれることで、効果が薄れたり、逆に副作用が強く出ることもあるため、慎重な判断が求められます。
特に、治療効果に直結しやすく、投与時間が厳密に決められている薬には注意が必要です。以下に、現場で特に注意が求められる薬剤を5つご紹介します。
- 抗がん薬(経口抗悪性腫瘍薬)(投与タイミングのズレが効果や副作用に直結)
- 循環作動薬(心拍数や血圧に影響する薬:例:ビソプロロール、アムロジピン、ジゴキシンなど)
- 抗凝固薬・抗血小板薬(いわゆる「血液サラサラの薬」)
- 抗てんかん薬(血中濃度の急変で発作のリスクが上昇)
- 抗菌薬(抗生物質)(不十分な投与が耐性菌の原因に)
これらの薬を服用中で、注入できない、または予定時間が大きくずれそうな場合は、自己判断を避け、必ずかかりつけ医や訪問看護師に相談することが大切です。
「あとでまとめて入れればいいかも」と思っても、時間管理が治療そのものである薬もあるという意識を持ちましょう。
確認すること=命を守ることにつながります。
予防の工夫と、安心して介護するために
毎回のフラッシュを忘れずに
最も効果的な予防は、注入や薬のあとに必ずぬるま湯で洗浄することです。
粉薬を使うときは、しっかり溶かしてから投与し、必ず水で流すのを忘れずに。
また、洗浄の習慣が自然に身につくよう、冷蔵庫や壁に「フラッシュチェックリスト」を貼っておくのもおすすめです。
「全部自分でやらなきゃ」と思わなくていい
詰まりが起きたとき、「私のせいかも」「失敗したかも」と感じてしまうことは、誰にでもあります。
でも、介護は“うまくやること”よりも、“迷ったら相談できること”が何より大切です。
あなたは、すでに十分頑張っています。1人で抱えず、支え合いながら乗り越えましょう。
最後に:迷ったときのチェックリスト
- □ 最後の注入後、洗浄をしたか?
- □ ぬるま湯で軽くフラッシュしたか?
- □ チューブの折れやねじれがないか確認したか?
- □ シリンジや器具の劣化はないか?
- □ 嘔吐や腹痛などの症状が出ていないか?
- □ このまま続けていいのか、不安を感じていないか?
2つ以上該当する場合は、迷わず医療機関や訪問看護師へ相談するのがおすすめです。
この記事が、あなたの迷いや不安を少しでも軽くできたなら嬉しいです。
よろしければSNSでのシェアや、コメントでの体験の共有をお願いいたします。
その言葉が、次に同じ悩みを抱える誰かの助けになります。
このページをブックマークしておけば、いつでも確認できます。
いざという時の安心のために、ぜひ保存しておいてください。
不安になったら、一人で抱え込まず、この記事を開いて確認しましょう。
他にも、下記テーマの記事があります。
- こけるときはこける、ケガをさせないことが大事
- その治療、本当に必要ですか?
- その薬、本当に必要ですか?
- もう解放されたいと思うその気持ち、持っていていいんです!
- カロリー重視でOK
- キーパーソンとは
- ケアマネージャーとは
- 人工肛門について
- 介護のSOS
- 介護保険のはなし
- 入所型施設について
- 包括支援センターと保健師
- 医療保険について
- 吸引について
- 圧迫骨折は入院させないのもひとつの手
- 在宅酸素について
- 排泄だけがネックなら、受け入れる覚悟を持とう
- 病院について
- 看護小規模多機能
- 経管栄養について
- 認知症に悩むあなたへ:在宅編
- 認知症に悩むあなたへ:病院、施設編
- 通所型施設について
- 高齢者はより感覚的で、感情で生きている
あなたのケアの一歩が、明日の安心につながりますように。