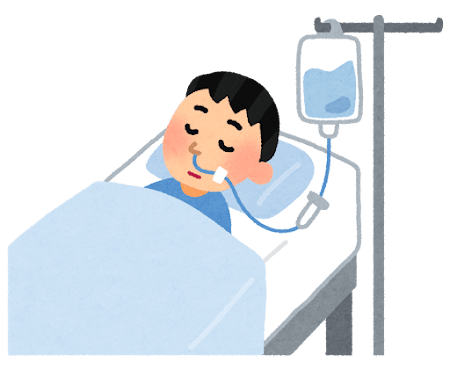当ブログでは、キーパーソンが悩む気持ちを基にタグ付けしています。ぜひほかの記事も読んでみてください。
きちんと向き合いたい このままでいいのか迷っている もっとラクに考えたい 一人で抱えるのは限界 何かを変えたいと思っている 家族の中で孤立している 後悔したくない 情報が足りなくて不安 本人の気持ちを優先したい 決めなきゃいけないけど決められない 疲れていることに気づかれたくない 相手を大切にしたいけど自分も大事にしたい 自分の気持ちに向き合いたい 話しづらい空気を感じている 認知症対応に限界を感じている 誰かに背中を押してほしい 誰にも相談できないまま抱えている
「私には無理かも…」
在宅で吸引に初めて向き合ったご家族が、ぽつりとつぶやきました。
私は回復期病棟で看護師として働き、たくさんの方が「怖い」と感じる場面に立ち会ってきました。
最初から完璧にできる人はいません。
でも、一歩ずつ慣れていった先に、自分を誇れる瞬間が必ず訪れます。
この記事では、在宅吸引に不安を抱えるあなたに、
「何から始めればいいか」「どう乗り越えられるか」を、
看護師の現場感覚で、やさしく丁寧にナビゲートします。
吸引とは?役割と必要性
吸引とは何か?【呼吸を守るケア】
吸引とは、口や鼻にたまった唾液や痰を吸い取り、呼吸を助けるケアのことです。
「医療行為」という印象が強いかもしれませんが、家族でもできるサポートです。
なぜ吸引が必要になる?【病気と筋力低下】
脳卒中やALS、重度の認知症などでは、唾液や痰を飲み込む力が落ちます。
そのままだと窒息や肺炎のリスクが高まるため、吸引が必要になります。
在宅で吸引が必要なケース【家族が支える力】
たとえば、
- 脳卒中後の飲み込み障害
- 気管切開後の呼吸管理
- 高齢者の慢性呼吸器疾患
こうした場合、在宅でも吸引が欠かせません。
吸引の種類と基本知識
口腔内吸引【まずは口からスタート】
口の中にたまった唾液や痰を、やわらかいチューブでやさしく取り除きます。
見える範囲から取り除くので、比較的取り組みやすい吸引方法です。
鼻腔内吸引【鼻水で呼吸が苦しいときに】
鼻づまりがひどいとき、細いカテーテルを使って鼻の中の分泌物を吸引します。
事前に生理食塩水を使うと、負担をぐっと減らせます。
気管内吸引【気管切開患者さんのケア】
気管切開部の管理には、吸引が欠かせません。
手洗い、機材の準備、酸素チェックを確実に行うことで、安全に行えます。
在宅吸引を始める前に知っておくこと
吸引は医療行為?【安心して取り組むために】
在宅で吸引を行うには、医師の指示と研修が必要です。
指示書をもらったら、大切に保管しましょう。
迷ったときは、医療機関に遠慮なく相談してください。
吸引の学び方【不安を減らす練習】
病院や訪問看護では、家族向けの吸引講習を実施しています。
マネキン練習や、実際の患者さんをサポートする場面を見学することで、確実な技術が身につきます。
自宅で練習するときのコツ【10分から始めよう】
いきなり完璧を目指さなくて大丈夫です。
家族で10分だけ、吸引の動作を練習しておくと、自然に自信がついてきます。
現場で見た成功例と成長のストーリー
実際にできるようになった家族の声
「最初は怖かった。でも、今は歯磨きと同じ感覚です。」
そんな言葉を、私は何度も聞いてきました。
吸引がもたらす家族の絆
吸引は、単なる医療行為ではありません。
患者さんの「生きる力」を支え、家族との絆を深める温かいケアでもあります。
まとめ:吸引は一歩ずつ、できるケアです
吸引ケアに不安を感じるのは、誰でも同じです。
大切なのは、焦らず、少しずつ進めること。
チェックリストで振り返りましょう。
✅ 吸引の役割を理解した
✅ 医師の指示書を受け取った
✅ 実技研修を受講した
✅ 自宅で短時間でも練習した
✅ 患者さんの呼吸や顔色を観察できる
✅ 不安があればすぐ相談できる
✅ 家族で支え合う意識を持った
小さな一歩が、大きな安心につながります。
この記事が、あなたの大切な人を守る力になりますように。
もしこの記事が役に立ったと感じたら、ぜひSNSでシェアしたり、コメントであなたの思いを聞かせてくださいね!