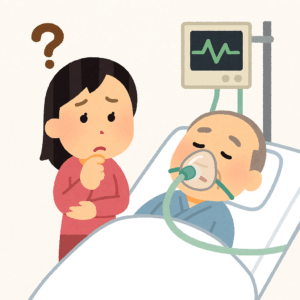「延命治療はしないでください」
そう言った娘さんの目に、涙が浮かんでいました。
病棟でご家族と話す中で、こうした場面にたびたび出会います。「延命か、そうでないか」──その判断は、簡単ではありません。
「やらない後悔」「やった後悔」。どちらにも、深い葛藤があります。
本記事では、現場でたくさんの家族と対話してきた経験をもとに、「どちらが正しいか」ではなく、「どうすれば納得できるか」をテーマに、5つの視点から考えてみます。
治療の意味を考える
延命とは何かを知る
言葉に隠れた前提を疑う
「延命」という言葉には、ネガティブな印象がつきまといますが、そもそも何を意味しているのか。人工呼吸器や経管栄養など、生命を維持する医療行為の総称として使われることが多いですが、必ずしも「苦しみを長引かせるもの」ではありません。重要なのは、その医療が「生きたい気持ち」に沿っているかどうかです。
現場では、「治す」ための医療と、「生きるためのサポート」の区別が曖昧なまま判断が迫られることがあります。まずはその違いを整理し、選択の前提を共有することが大切です。
本人の価値観を尊重する
「本人の意思」へのまなざし
言葉にできなかった願いを想像する
高齢で意思表示が難しい方の場合でも、「どんな人生を歩んできたか」「どういう考え方の人だったか」という背景から、その人らしい選択を尊重するヒントが見えてくることがあります。
あるご家族は、認知症で話せなくなったお母さんについて「母は昔から“無理して長生きしたくない”って言ってた」と話してくれました。その言葉をきっかけに、治療の方針が固まったこともありました。
治療後の生活をイメージする
延命の先にある時間
生活の質(QOL)を考える
延命治療が成功したとしても、その先にある生活が本人や家族にとってどのようなものになるのかを想像してみてください。
人工呼吸器で寝たきりの状態になるかもしれない、経管栄養で会話もできないまま過ごすことになるかもしれない。
そうした可能性を、「現実的に」想像しておくことが、後悔の少ない判断につながります。
日本老年医学会などでも、治療の「効果」だけでなく、回復後のQOLや本人の満足度を評価に含めるべきとされています。
家族の負担を見つめ直す
介護と感情のはざまで
看る側の「これ以上は無理」も尊重する
「親の命を自分が決めていいのか」という罪悪感に苦しむ方も多いですが、現実には介護や経済的な負担、精神的な限界もあります。それを無理に押し殺して「最善」を目指そうとすると、結果的に共倒れになることもあります。
「できるだけのことをした」と思えるラインを、家族内で確認し合うことも、ひとつの正解です。
急がない決断を
即答を求められたときこそ
医療者に相談するタイミング
延命治療の判断は、急に迫られることがあります。「今決めてください」と言われても、即答しないといけないわけではありません。治療内容や代替案、本人の状況を踏まえて説明を求めるのは当然の権利です。
「何をすればいいか分からない」と感じたら、緩和ケアチームや退院調整看護師、地域包括支援センターなども頼ってみてください。医師や看護師との対話を重ねていく中で、気持ちが整理されていくことも少なくありません。
まとめ:納得できる選択のために
チェックリスト(判断前に振り返りたい5項)
- 治療の目的と限界を理解できていますか?
- 本人の生き方や価値観に耳を傾けていますか?
- 延命治療後の生活を具体的に想像できていますか?
- 家族自身の負担と限界を見つめ直しましたか?
- 急がず、相談できる窓口を確保していますか?
人生の最終段階において、「正しいかどうか」ではなく、「納得できるかどうか」が何より大切だと、私は現場で感じています。
たったひとつの正解ではなく、ご家族にとって意味のある選択になるように。
その道筋の一助になれば嬉しいです。