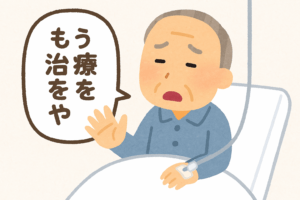導入文
「つらいって言ってるのに、やっぱり治療は続けなきゃいけないんでしょうか?」
あるご家族が、面会の後にふと口にした言葉です。
高齢者医療では、正解が一つではない選択が多く、悩みは深くなりがちです。看護師として現場にいると、「もっと早く、誰かに話せていたら」と思う瞬間に何度も出会います。
この記事では、「治療がつらい」と言われたときに、ご家族が立ち止まりながらも納得して前を向けるよう、看護師としてお伝えしたい5つの判断軸をご紹介します。
治療の目的を再確認する
目的は「病気を治すこと」だけではない
病名を告げられた瞬間、目指すべきは「治療=完治」と考えがちです。しかし高齢者医療では、完治よりも「生活の質」を重視する視点もあります。
痛みを和らげる、食事を取れるようにする、穏やかに過ごす時間を守る……こうした目的も、医療の大切な役割です。
「この治療は、何のために続けているのか?」と立ち返ることで、見えてくる選択肢があるかもしれません。
負担と効果のバランスを見る
「続けるだけでしんどい」治療に意味はあるか
現場では、治療の副作用で動けなくなったり、日常生活が大きく制限される方に出会います。
ある患者さんは、週2回の通院治療を続けていましたが、「病院に行くために生活しているみたい」と感じるようになったそうです。
治療の恩恵と負担を丁寧に見比べることは、ご本人とご家族の将来にとって、非常に重要です。医学的な“正しさ”と、生活の“心地よさ”が一致しない場面こそ、考え直すチャンスです。
意思を尊重する姿勢を持つ
治療に対する気持ちは言葉だけで量れない
「嫌とは言わないけど、うれしそうでもない」。
そんな表情の変化を、長年そばにいたご家族は敏感に感じ取ります。言葉で伝えられない方の意思確認は難しいですが、看護師やリハビリ職と協力して、“ご本人らしさ”を丁寧に探ることができます。
本人の希望が汲み取れないときには、「これまでの人生で何を大切にしてきたか」という視点も判断の手がかりになります。
家族自身の限界を見つめる
「もう無理かも」と思った自分を責めないで
介護の場では、支える側の我慢が前提になりがちです。でも、我慢しすぎて心が壊れてしまえば、誰のためにもなりません。
「ここまで支えたけれど、そろそろ限界」と感じたら、それは十分頑張った証です。
そのときは、医療チームに気持ちを共有してみてください。負担を軽くするための選択肢が、きっと見つかります。
迷ったら専門家に相談する
一人で答えを出そうとしない
「周囲に迷惑をかけたくないから自分で決めなきゃ」と思い詰めてしまう方が少なくありません。
でも、治療やケアの方針は、多職種で考えるからこそ広がりが出ます。
地域包括支援センターや病院の相談窓口、訪問看護師など、第三者に話すことで、新たな視点を得ることができます。
まとめ:選択に「正解」はなくても、「納得」はできる
この記事では、治療を続けるか迷ったときに立ち返る5つの軸をお伝えしました。
判断軸チェックリスト
- □ 治療の目的は何か、明確になっているか?
- □ 治療の効果と負担は見合っているか?
- □ 本人の想いを丁寧に確認しているか?
- □ 家族の心身の限界を把握しているか?
- □ 専門職の意見を取り入れているか?
選んだ道が「完璧」である必要はありません。
大切なのは、後悔しないように、いま出来る対話と選択を重ねていくことです。
この記事が、その一助になれば嬉しいです。