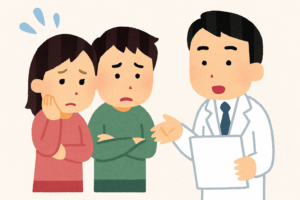「お母さん、もう治療やめたいって言ってるの…」
病室の隅で、娘さんがぽつりとつぶやいた一言が忘れられません。
高齢の親の治療選択を家族が迫られたとき、「正解」が見えなくなってしまうのは決して珍しいことではありません。
この記事では、治療の選択に迷うご家族に向けて、「どう考えるか」「何を大切にすればよいか」という視点を5つにまとめてご紹介します。
専門的な話ではなく、看護師として現場でご家族に寄り添ってきた中で、実際に役立った考え方をお伝えします。
「後悔しない選択」をしたいと願うあなたのために──
ひとつでも心に残る言葉があれば嬉しいです。
治療選択に必要な5つの視点
患者の価値観を探る
今までの生き方にヒントがある
治療を選ぶ際には、医学的な正しさよりも「その人らしさ」に注目することが重要です。
たとえば、「なるべく人に迷惑をかけたくない」「仕事をやりきるまでは頑張りたい」という言葉の裏に、人生の価値観が見えてきます。
本人がこれまでどう生きてきたか。その延長線上にある選択が、結果として納得感を生み出します。
医療の目的を再確認する
治すため?和らげるため?
治療のゴールは「完治」だけではありません。痛みを軽減する、呼吸を楽にする、ごはんが食べられるようにする──それも立派な治療です。
厚労省のガイドラインでも、本人のQOL(生活の質)を重視した緩和ケアや支持療法の有効性が示されています(参考:厚生労働省 令和4年診療報酬改定資料)。
治療の目的を共有することで、「何のための治療か」が明確になり、判断の軸がぶれにくくなります。
迷いは悪ではない
悩む時間が大切な意味を持つ
迷うという行為には、「大切にしたいものがある」という前提があります。
治療の選択に迷う家族は、それだけ真剣に患者の人生と向き合っているということ。
私たち医療者も、すぐに答えを出すことが最善だとは思っていません。迷っていいんです。迷いながら進む道にも、意味があると信じています。
治療以外の選択肢も知る
「治療しない」もひとつの選択肢
選択肢は「する」か「しない」かだけではありません。
症状を和らげるだけの緩和ケアや、ご自宅で自然な経過を見守る在宅療養という形もあります。
大切なのは、選択肢を知ったうえで本人や家族に合った方法を選べることです。
「何もしない」ではなく、「何をしないかを選ぶ」と考えてみてください。
支えてくれる人を増やす
一人で抱えない仕組みをつくる
治療の選択は、家族にとっても大きなプレッシャーになります。
ケアマネジャー、地域包括支援センター、訪問看護師など、頼れる存在を一緒に巻き込んでいくことが、負担の軽減につながります。
ときには、病院の医療ソーシャルワーカーに相談するのも有効です。
まとめ:治療を選べないときのチェックポイント
最後に、この記事の内容をポイントで振り返ります。
- 【価値観】患者の生き方をヒントにする
- 【目的確認】治療の「目的」を再確認する
- 【迷い】迷ってよいと自分を認める
- 【選択肢】治療以外の方法も知る
- 【支援】一人で決めず、支援を活用する
どれも特別な知識は必要ありません。
まずは今日、「あなたがどんな思いで迷っているのか」を誰かに話すことから始めてみませんか。
▼チェックリストで振り返り
- □ 本人の希望や価値観を考慮したか
- □ 治療の目的を家族間で話し合ったか
- □ 他の選択肢を医療者に聞いてみたか
- □ 支えてくれる人に相談できているか
- □ 自分自身の気持ちも大切にできているか