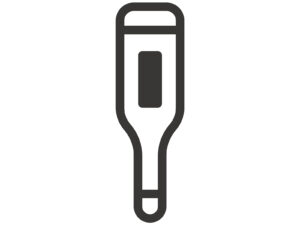「また点滴ですか…」
その言葉には、繰り返される発熱と治療の流れに、家族としての不安や疲労がにじんでいました。
高齢の方が発熱を繰り返すと、「また感染かな」「また点滴だ」となることが多くあります。特に尿路感染症は目に見えづらく、本人が症状を訴えにくい分、早期発見が難しい側面もあります。
この記事では、実際に“治療のループ”を断ち切った家族がとった5つの選択肢を紹介します。気づきや行動のヒントを通して、これからの介護に前向きな選択ができるようサポートできれば幸いです。
なぜ感染が繰り返されるのか?
発熱の背景にある生活要因
高齢者の発熱には、体力や免疫の低下、排尿機能の変化、栄養不足など多くの生活要因が重なっています。
「治ったと思っていたのにまた熱が出た」というケースは、生活のどこかに見直すべきポイントがある可能性があります。
一時的な治療がループの原因に
点滴で熱が下がっても、根本的な原因がそのままであれば、また同じような状況が繰り返されてしまいます。これは、症状の対応だけにとどまり、「なぜ起きたか」に踏み込めていないことが要因です。
家族の“違和感”が突破口になる
ある家族は、「いつもよりトイレに行っていない」「口数が減った」などの小さな変化に気づき、記録を取り始めました。その結果、医療者への相談が具体的になり、治療方針の選択肢が増えたそうです。
家族が実践した5つの工夫
気づきを“記録”という形に
医師に「熱が出た」と伝えるより、「水分は1日〇ml、尿の色は濃い」など具体的に話すほうが、的確な判断につながります。介護記録は、医療チームとの大切な橋渡しになります。
入院以外の選択肢を知っていた
「毎回点滴ではなく、経口の抗生剤で様子を見たい」と家族が伝えたことで、医師との対話が生まれたケースもあります。信頼関係があれば、治療の柔軟性も広がります。
排泄のケアを見直す
おむつ交換や陰部洗浄を丁寧にすることで、尿路感染のリスクは確実に下がります。毎日繰り返すケアだからこそ、基本に立ち返ることが予防になります。
水分摂取の工夫を続けた
「水は飲まないけど、果物のゼリーなら食べる」といった工夫も、脱水予防に効果的です。食事やおやつの中に、水分を“自然に”取り込める工夫がポイントです。
家族が「変化の語り手」になる
本人が自分の変化を言葉にできない分、家族の観察が頼りになります。「ちょっとした違和感」を言語化する力が、ループから抜け出すきっかけになります。
トラブルを防ぐ日常ケア
日々の工夫が最大の予防策
感染予防は、専門的な処置だけではありません。排尿パターンの把握や、定期的な水分補給、陰部のケアといった毎日の積み重ねが鍵となります。
生活リズムの中に予防を組み込む
「起床後に白湯を飲む」「おやつは水分多めのフルーツゼリーにする」など、小さな工夫が習慣化することで、大きな予防効果につながります。
まとめ:点滴を繰り返さないために
発熱のたびに入院や点滴を繰り返す…そのたびに介護者も不安や疲労を感じます。
しかし、生活に潜む再発の原因を見つめ直すことで、繰り返しの連鎖から抜け出す道が見えてきます。
以下のポイントを押さえ、できるところから取り組んでみてください。
- 家族の気づきや記録が医療判断を助ける
- 「再発しない生活」を意識した排泄・水分管理を行う
- 水分摂取は「飲み物」以外からも取り入れる
- 医師と“選択肢のある会話”をするための準備をする
- 感染のサインは「発熱」だけではなく、行動や言動の変化にも現れる
介護に正解はありません。でも、「またか…」と感じたときこそ、変化を起こすチャンスかもしれません。
あなたの経験や工夫も、ぜひSNSやコメントで教えてください。