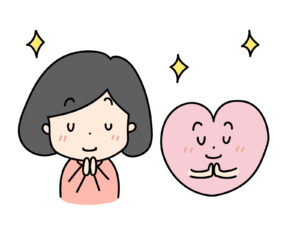はじめに:その“わからなさ”が、気づきの入り口かもしれません
「言ってることが分からない…」
「どうしたいのか教えてくれたらいいのに…」
介護をしていると、こんな風に思ってしまうことがありますよね。
私自身、回復期病棟で関わってきた中で、「わからなさ」に戸惑い、心の中でため息をついたことが何度もあります。
でもあるとき、ふと思ったんです。
「わからない」という感情は、関わっている証拠だと。
そして、その不安や違和感の中に、相手からの“サイン”が隠れていることに気づいたんです。
この記事では、「わからない不安」に向き合いながら、光を見つけた5つのエピソードを紹介します。
サインに気づく「視点」を持つ
「何か変だな」がヒントになる
「表情が固いな」「今日は動きがぎこちない気がする」
そんな違和感に気づくことで、身体の不調や不安に早く対処できることがあります。
ある方は、座り方が少し傾いているだけで、腰の痛みを我慢していたことが分かりました。
小さな変化に気づく視点が、安心を生む第一歩になります。
無言の時間も観察してみる
言葉がないとき、「何も伝えたいことがない」と思ってしまいがちですが、
実は無言の時間ほど、表情やしぐさから伝わってくることが多いんです。
まばたきの回数や手の動きなど、“沈黙のメッセージ”に気づけるかどうかがカギです。
「わかろうとすること」が負担になっていないか
完全な理解を求めすぎない
「全部わかってあげなきゃ」と思うほど、こちらが疲れてしまいます。
でも、本当は**“完全に理解する”ことより、“寄り添う姿勢”の方が相手を安心させる**のです。
わからないと感じたときこそ、「そばにいること」の意味を見つめ直してみてください。
沈黙を共有するという関わり方
ある方との関わりで、言葉では何も返ってこなかったけれど、
そっと手を握ったときに、目に涙が浮かんだことがありました。
言葉にならない想いも、静かな時間を共有することで伝わる。
そんな経験が、私の介護観を変えてくれました。
「背景」を知ると、理解が深まる
感情の出し方にも理由がある
「ありがとう」と言いながらも、どこか壁を感じる方。
その方が過去に、ずっと“がまんすること”を習慣にしてきたと知って、
表面の言葉ではなく、その人の“背景”を想像するようになりました。
相手の過去が、今の言動をつくる
どんな環境で育ち、どんな役割を担ってきたのか。
その人の人生に触れることで、なぜその言い方をするのか、なぜその反応になるのかが見えてきます。
「今ここ」だけを見ずに、「これまでの道のり」も想像してみることが、理解へのカギです。
まとめ:不安の先に、やさしい関係が待っている
「わからない」と感じたとき、無理に理解しようとしなくても大丈夫です。
その感情こそが、気づきのスタートラインかもしれません。
✅ 不安を光に変えるためのチェックリスト
☑ 表情やしぐさの変化に敏感になれているか
☑ 「理解できない自分」を責めていないか
☑ 無理に答えを求めすぎていないか
☑ 相手の過去や価値観を想像してみたか
☑ 沈黙を共有する関係性も意識できているか
あなたの「わからない」は、優しさの入り口です。
この気づきが、あなたの介護に少しでも安心をもたらしますように。
感想や体験談があれば、SNSでぜひシェアしてください。
一緒に、この気づきを広げていきましょう。