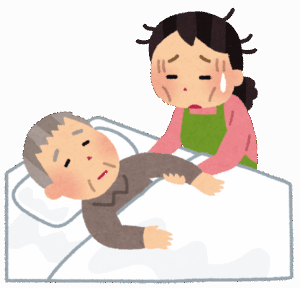「伝わらない…」と感じた瞬間のあなたへ
「何回言っても通じない」「また話がループしてる」——
介護の会話で、こんな風に思ったことはありませんか?
先日、病棟で出会った娘さんは「朝ごはんを食べたのに『まだ?』って聞かれて…もう疲れちゃいました」と、ぽつりと話してくれました。その表情には、笑顔とため息が同居していました。
この記事では、「会話がつらい」と感じたときに、気持ちを少しだけ整えるための6つの視点をお伝えします。
つながりたいのに、すれ違ってしまう。
そんなあなたの心に、そっと寄り添えますように。
通じ合えないのは、失敗じゃない
話がかみ合わないと、なぜこんなにつらいのか
介護の中でよくある「通じない会話」。
説明しても伝わらない、返事がかみ合わない——その積み重ねは、想像以上に心を消耗させます。
でもそれは、あなたがダメだからではありません。
高齢者は年齢とともに記憶力や理解力が変化し、「今ここにある感覚」を大切に生きるようになります。
話がかみ合わないのではなく、“見ている世界が違う”と考えてみてください。
相手を責めず、自分も責めず。ズレを前提にした会話は、気持ちにゆとりをくれます。
言葉の奥にある“安心”を届けよう
通じない言葉に疲れたときは、言葉を減らす選択も大切です。
手を握る、目を合わせる、静かに隣に座る——その空気ごと「大丈夫だよ」と伝える方法もあります。
言語以外のコミュニケーション(非言語)は、特に認知症の方にとって重要な安心材料です。
あなたの“その場にいる姿”が、何よりのメッセージになることもあるのです。
苦しさの裏にある気持ちと向き合う
「わかってほしかった」が根っこにある
通じない会話がつらいと感じる背景には、
「わたしの気持ちをわかってほしかった」「努力を認めてほしかった」
という、切実な想いがあることが少なくありません。
自分では気づかないうちに、頑張りが報われない苦しさが蓄積されているのです。
まずは、自分が「伝えたかった気持ち」に目を向けてみましょう。
その気持ちに気づくことは、自分を癒す第一歩です。
自分を責めるより、「できたこと」に目を向けて
介護の中では、「もっと優しく言えたかも」「言いすぎたかも」と自己嫌悪に陥る場面がよくあります。
けれど、すべての会話がうまくいく必要はありません。
今日怒ってしまったとしても、昨日は優しくできたかもしれない。
その“できた日”の自分を覚えておくことが、次の優しさにつながります。
感情に波があるのは当然。
うまくいかない日は、心の休息日と割り切っていいのです。
会話に頼らず、つながる方法を持とう
言葉を使わない時間も大切に
会話だけが、つながる手段ではありません。
音楽、昔の写真、天気の話、散歩中の風景。
「一緒に感じる体験」が、言葉以上に記憶に残ることもあります。
特に五感を使った体験は、感情と記憶を深く結びつけるとされています(※参考:加齢と感覚記憶に関する研究)。
“うまく話す”より、“一緒に楽しむ”を意識してみてください。
自分の心を整えるちいさな工夫
つらさを感じたときは、「つらい」と思う自分を否定しないことが大切です。
深呼吸をする、ちょっと席を離れる、好きな香りをかぐ——
それだけでも脳はリラックスモードに切り替わります。
完璧なケアを目指すのではなく、心が整う時間をこまめに持つ。
その積み重ねが、あなたの介護力を支えてくれます。
まとめ:つながりは、言葉を超えて
言葉がすれ違っても、気持ちはちゃんと届いている——
介護の現場で何度も目にしてきた、真実です。
完璧な会話でなくても、まっすぐな想いはにじみ出ます。
だからこそ、今日もあなたが“そばにいる”ことに、意味があります。
疲れたときには、言葉を手放す勇気を。
気持ちが重なった瞬間を、大切に。
✅ チェックリスト(心を軽くする6つの視点)
- 会話が通じなくても、それは失敗ではない
- 非言語のつながりにも価値がある
- 苦しさの根っこに「わかってほしい」がある
- 自分の小さな“できた”を見つける
- 五感を使った体験を共有する
- 自分の心を整える方法を持つ
▶共感したらSNSでシェアを!
「うちも一緒だった」という言葉が、誰かの救いになるかもしれません。
ご意見や経験談のコメントもお待ちしています。
一緒に、“伝わらない日も、つながれる介護”を広げていきましょう。