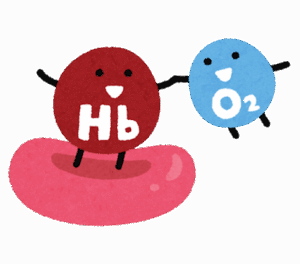「お父さん、息がしづらそう…でもどうしたらいいの?」
そんなふうに、酸素療法中のご家族の呼吸が乱れている場面に直面し、焦りと不安に包まれた経験はありませんか?
私は回復期病棟で働く看護師として、在宅酸素療法(HOT)を受ける多くの患者さんとご家族を支えてきました。中でも「酸素は流れているのに苦しそう」という場面は、想像以上に多く、かつ見逃されがちな危険信号でもあります。
この記事では、在宅酸素療法中に呼吸が苦しくなったときに、慌てずに確認すべき7つの行動を、現場での経験を交えながらわかりやすくご紹介します。
状況を落ち着いて確認する
呼吸の観察から始めよう
まず、「何かおかしい」と感じたら、すぐに機器に飛びつくのではなく、呼吸そのものを観察することが大切です。
数値よりも“いつもと違う”に注目
酸素流量や機器の設定が正常でも、呼吸の速さや肩の動き、表情、唇や爪の色が普段と違うなら、それは異常のサインです。
かつて訪問時、酸素は適正に供給されていたにもかかわらず、便秘でお腹が張っていた方が呼吸苦を訴えていたケースがありました。原因を解消すると、酸素の調整なしに改善しました。
比べるべきは「いつもの呼吸」
ご本人の“ふだんの呼吸”を基準に、「今日は明らかに違うかどうか」を判断しましょう。その視点が、誤った判断を防ぎます。
酸素が届いているか確認する
次に、酸素がきちんと本人に届いているかをチェックします。
チューブとカニューラを見直す
チューブがねじれていたり、家具に挟まっていたりしませんか?カニューラが鼻から外れていたり、結露や分泌物で詰まっている場合もあります。
あるお宅では、酸素チューブがリクライニングチェアの脚に潰されており、酸素がほとんど流れていませんでした。
流量計の確認も忘れずに
機械が作動していても、「スタンバイ状態」になっていることもあります。泡が動いているか、設定が医師の指示通りか確認しましょう。
💡 ポイント:
壁や酸素機器に「①チューブ②流量③カニューラ」と書いたメモを貼っておくと、パニック時の手助けになります。
まずは落ち着くこと
本人が苦しそうにしていると、つい焦ってしまいます。しかし、介護者の不安はご本人に伝わり、症状を悪化させることもあるのです。
深呼吸して、一言添える
「大丈夫、確認するね」
そう声をかけるだけで、安心感を与えられます。
あるご家族は、「私が『どうしたの!?』と焦って叫んでいたら、余計に苦しそうに見えた」と話してくれました。まずは深呼吸を。落ち着きは“治療の一部”です。
対応手順を可視化する
「どうすればよかったんだろう…」を防ぐには、行動のチェックリストを目に見える場所に貼っておくことです。
例:
- 呼吸の様子を見る
- チューブと流量を確認
- 異常時は酸素業者に連絡
- 必要なら救急車を呼ぶ
4行のメモだけでも、安心感が全然違います。
次に取るべき対応
非常用酸素への切り替え
濃縮器の故障や停電時には、非常用ボンベや携帯酸素に切り替える必要があります。
非常用ボンベの使い方を確認
「予備はあるけど使ったことがない」
そんな声をよく聞きます。
- バルブの開け方
- 流量の調整方法
- 接続方法
これらをあらかじめ練習しておきましょう。
家族全員が扱えるように
酸素の管理が一人に偏っていると、いざという時に対応できないことも。家族みんなで10分だけ「酸素の避難訓練」をするのもおすすめです。
酸素業者に連絡する
異音、匂い、酸素が出ていない等、いつもと違うと感じたら業者に相談しましょう。
「まだ動いてるから大丈夫」は危険
機器は突然止まることもあります。早めの連絡が故障や事故を防ぎます。
通報時には、
- 機種名
- 症状や警告音の有無
- 現在の流量設定
を伝えると、対応がスムーズになります。
自己判断で流量は変えない
「ちょっと多めにした方が楽になるかも」は、逆効果になることも。特にCOPDの方には注意が必要です。
救急車を呼ぶべきタイミング
酸素が流れていても、呼吸状態が明らかに悪化しているなら、迷わず119番してください。
見逃してはいけない症状
- 唇や爪が紫色
- 意識がぼんやりしている
- 酸素をつけていても改善しない
- 呼吸数が異常に速い、あるいは遅い
救急搬送されたご家族が後から「こんなことで呼んでよかったのかな…」と不安そうに話すことがありますが、後悔するより、迷って呼んだ方が良いのです。
通報時の伝え方を決めておく
例:
「酸素療法中ですが、呼吸が苦しそうです。機器は作動していますが改善しません。」
こうしたフレーズをメモしておくだけで、通報時に慌てずにすみます。
次に備える準備
緊急対応のルーティン化
緊急時に判断力を失わないためには、普段からの備えが鍵です。
電話番号を目立つところに
酸素業者、かかりつけ医、病院、119、家族の連絡先を、目に入りやすい場所にまとめておきましょう。
定期的に“予行演習”を
「酸素が止まったら何をするか」など、家族で確認する時間を作りましょう。難しく考えず、月1回の夕食後などに実施するだけでも安心感が違います。
共有できる対応マニュアルを
主介護者だけが把握していても、いざというときに不在だと混乱します。
シンプルな印刷資料を作成
- 機器の使い方
- 故障時の連絡先
- 異常時の判断ポイント
これらを一冊のファイルやバインダーにまとめ、「酸素対応マニュアル」として家族と共有しておくのがおすすめです。
まとめ:不安の種を、備えに変える
呼吸が苦しいとき、介護する側もパニックになります。
でも、落ち着いて観察し、確認し、連絡し、備えていれば、多くのトラブルは未然に防げます。
✅ 緊急時チェックリスト
- 呼吸の様子と皮膚の色を観察
- チューブ・流量・カニューラを確認
- 非常用酸素の使用方法を家族で共有
- 酸素業者に早めに連絡
- 救急の判断基準を把握
- 対応マニュアルを自宅に常備
- 家族で定期的にシミュレーション
💬 この記事が役立ったと感じたら、ぜひSNSでシェアしてください。
「同じように不安だった」と感じる方が、あなたの投稿で救われるかもしれません。