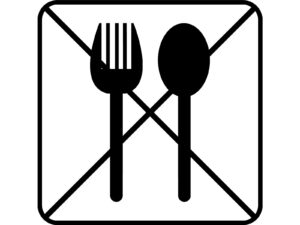朝食べない、昼も寝てばかり
ある日、朝食に手をつけず、昼過ぎまでぐっすり眠っていた高齢女性がいました。
私は「食べない」「寝てばかり」という状態を目にすると、つい認知症の進行を疑ってしまいます。
ですが、それが必ずしも“病気の悪化”とは限らないことを、臨床現場で多く学んできました。
この記事では、介護現場でよく見かける“変化のサイン”について、医療職の視点と家族の感情の両方を交えながら解説します。
焦って結論を出す前に、「何が背景にあるのか?」を一緒に見直してみませんか。
① 水分不足と脱水
認知症の方が食事を拒むとき、背景に「脱水」があることがあります。
喉の渇きを感じにくくなる高齢者は、体内の水分が不足していても本人が気づけない場合があります。
実際、脱水状態では唾液の分泌が減って飲み込みが悪くなり、食欲も落ちるとされています。
日本老年医学会によると、脱水の初期症状には倦怠感、食欲不振、眠気などがあり、早期の気づきが重要とされています。
口の乾き、尿の量や色など、日々の観察でわかることも多いです。
「食べない」ではなく「飲めていないかも?」という視点も、持っておきたいですね。
② 服薬の影響
「最近、薬が変わった」「眠気が強くなった気がする」
こうした変化があった場合、服薬が影響している可能性があります。
一部の抗認知症薬や精神安定剤には、眠気や食欲不振といった副作用が見られることがあります。
実際に、ある利用者さんは新しい薬に切り替えてから1週間ほどで食事量が半分になりました。
医師と相談し、処方を再調整してから少しずつ回復していきました。
薬の変化は、見落としがちですが重要な視点です。
日々の記録や“いつから変わったか”を把握することで、医療者との連携もスムーズになります。
③ 周囲の“圧”による拒食
「食べないの?」「全部食べようね」
そんな励ましのつもりの声かけが、時に心理的な負担となってしまうことがあります。
あるご家族が毎日、食事を強く勧めていた利用者さんは、徐々に食卓に座るのも嫌がるようになっていきました。
本人のペースや気分が尊重されていないと感じると、「食べたくない」が「食べたくない気持ちを表す手段」に変わることもあります。
高齢者の食事には、栄養摂取以上に“心の交流”の要素が大きく関わります。
「一口だけでも嬉しい」「食べられる時間にそっと寄り添う」ような工夫が、安心につながります。
④ 他疾患の見落とし
「認知症だから仕方ない」と思い込む前に、他の身体的な病気の可能性を探ることも大切です。
感染症、うつ症状、消化器系の不調などは、いずれも“食欲の低下”や“眠気”として現れることがあります。
実際に、軽度の尿路感染症だった利用者さんが、抗生剤の投与で急に元気を取り戻したケースもありました。
国立長寿医療研究センターによると、高齢者の感染症は発熱や痛みよりも「食べない」「寝る」などのサインが目立つ傾向があるとのこと。
小さな体調の変化も、「いつもと違う」と感じたら医療者に相談することで、早期発見につながります。
⑤ 本人の“終活的感覚”
「もう食べなくていいと思ってるのかもしれません」
そう話すご家族に、私はそっと頷いたことがあります。
認知症の方の中には、「人生を終える準備」をゆるやかに進めているような心理状態になる方もいます。
これを“終末期”と決めつけず、“本人の納得”として受け取る姿勢も時には必要です。
介護者としては切ない思いにもなりますが、その感情も含めて関わり続けることに意味があります。
「食べない」ことを“拒否”と見るか“選択”と見るかで、介護の質は変わってくると私は感じています。
環境と声かけで差が出る
同じ人でも、食べる環境が少し変わるだけで、食事の反応がまるで違ってくることがあります。
たとえば、照明を落として落ち着いた雰囲気にしたり、他の人の食事風景が見える場所に移動しただけで、自然とスプーンを持ち始めた方もいました。
環境刺激が過剰でも不足でも食欲に影響が出るため、「ちょうどいい」刺激量を探ることが大切です。
また、「◯◯さんも食べてるよ」「今日のおかず、好きそうだね」といった共感型の声かけが、気持ちを和らげてくれます。
日々の観察と微調整が、“その人らしい食事時間”を支えます。
一口でも“食べたい”気持ち
完食してもらうことがゴールではありません。
大事なのは、“その人が今食べたいと感じた一口”を尊重することです。
あるおばあさんが、スプーン一杯だけをゆっくり味わって「おいしいね」と言ってくれたとき、
その言葉に救われたのは、介助していたご家族の方でした。
食べることが喜びに変わる瞬間は、介護する側の心も軽くしてくれます。
“口に運ぶこと”そのものが、信頼とつながりを築く行為でもあるのだと感じます。
まとめ|気づくことから始まる介護
「認知症で食べない」「寝てばかり」
この状態だけを見て“重症”と決めつけるのではなく、背景にある小さな変化や気持ちに目を向けることが、よりよい介護につながります。
✅ 見直すべきポイントチェックリスト
- 水分摂取は足りているか?
- 薬の影響が出ていないか?
- 声かけや環境が過度になっていないか?
- 他の疾患を見落としていないか?
- 本人の“今の気持ち”に寄り添えているか?
小さな気づきが、大きな安心につながることがあります。
この記事が、少しでも介護のヒントになれば幸いです。
コメントやシェアも歓迎です。
あなたの経験が、誰かの支えになるかもしれません。