「退院してから思うように動けなくなったんです…」
そう語ったご家族の表情は、不安と戸惑いが入り混じっていました。
入院中にはリハビリも進んでいたはずなのに、自宅に戻ってからはむしろ生活の幅が狭まってしまう。そんな場面を、私は回復期病棟の看護師として何度も見てきました。
この記事では、**退院後の生活に潜む“回復を妨げる要因”**を5つに絞って解説します。日々の小さな習慣が、回復のスピードに大きく関わることがあるのです。
遅れを感じたときに見直すべき生活習慣
1. 長時間の座位が続いていませんか?
「なるべく動かないように」と思って座ってばかりいると、下半身の筋力は驚くほど早く落ちてしまいます。
特に高齢者では、1日中座った姿勢が続くと血流や心肺機能にも悪影響が出やすくなります。理想は「2時間に1度は立つ・歩く」を目標にすること。
リモコンを取りに立つ、洗面所に行く、台所で手を動かす——こうした小さな動作の積み重ねが、身体機能の維持には効果的です(日本老年医学会, 2020年)。
2. 栄養バランスは整っていますか?
「食べてるのに痩せてきた…」という相談はとても多いです。
見落としがちなのが、たんぱく質とエネルギーの不足。
年齢とともに食欲が落ちてきた方の場合、意識しなければ不足しがちです。
高齢者の栄養目安は、体重1kgあたり1.0〜1.2gのたんぱく質が推奨されています(厚生労働省「健康づくりのための身体活動・食生活指針」)。
市販の栄養補助食品や高カロリーデザートなどを上手に取り入れると、日々の食事でも負担が少なく補えます。
3. 会話や表情、減っていませんか?
自宅に戻って静かな生活になると、会話の量が減ってしまうことがあります。
でも実は、話すことは心身の活性化にとても大切。
言葉を交わす中で表情筋が刺激され、脳の働きも促されるとされています。
「今日寒いね」「ごはんおいしかったね」——そんな一言だけでも違います。
心理的な活力の維持が、活動意欲の回復につながっていきます。
4. つい手を貸しすぎていませんか?
「一人では難しそうだから…」と、日常の動作を全て手伝っていませんか?
それは優しさでありながら、“動く機会”を奪ってしまうことにもつながります。
たとえば、衣服の着脱では「上半身は手伝って、下半身は本人に任せる」といった部分的な介助にするだけでも違います。
“見守る勇気”を持つことが、本人の力を引き出すサポートになります。
5. 医療者や支援者との連携はできていますか?
「ちょっと気になるけど、相談していいのか分からない」——そんなときこそ、専門職との連携が役立ちます。
訪問看護やリハビリ、地域包括支援センターなど、情報共有できる窓口は複数あります。
家族だけで悩むよりも、「最近こんな様子です」と共有することで、必要な対処や支援につながることも少なくありません。
日々の様子を「気軽に書き留めて相談できる環境づくり」が、介護者自身の安心にもつながります。
まとめ:5つの生活習慣で見直したいポイント
以下の5点をチェックしてみてください:
- 長く座りすぎていないか?
- 食事内容のバランスは取れているか?
- 会話や笑顔が少なくなっていないか?
- 介助が“過剰”になっていないか?
- 専門職と十分に連携できているか?
どれか一つでも当てはまるなら、そこに改善のヒントがあります。
看護の現場では、「何か変えたとき」に回復が一気に進むケースもあります。
大きな決断ではなく、小さな生活の見直しから始めてみませんか?







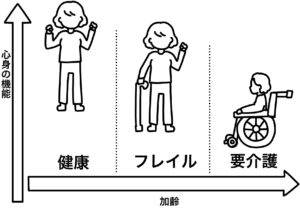
コメント
コメント一覧 (1件)
[…] あわせて読みたい 回復が遅い理由はコレ!圧迫骨折後に見直したい5つの生活習慣 「退院してから思うように動けなくなったんです…」そう語ったご家族の表情は、不安と戸惑いが […]